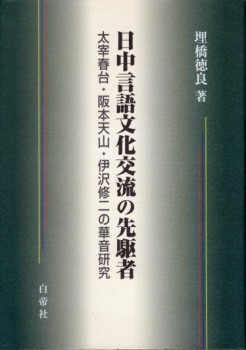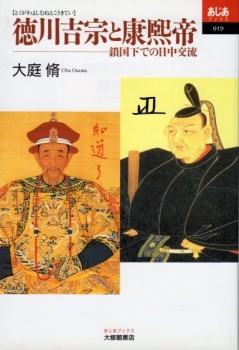![]()
![]()
体感!痛感?中国文化
第12回 唐人の寝言
話は50年以上も前にさかのぼる。大学受験でフウフウいっていたころ、ある受験雑誌に、「志望校に受かりたかったら齋藤秀三郎の『熟語本位 英和中辞典』を読め」という記事があった。辞書なのに「読め」とはまた不思議な、と思ったが、とにかく赤鉛筆で線をひきながら徹底的に読みまくれ、綴じ糸がきれそうになるまで読んだら「合格の赤飯を炊け」、と有無をいわせない推薦ぶりについ買ってしまった。
確かに特徴のある辞書で、forは8頁、withは10頁、toに到っては12頁にわたってびっしりと記述がある。活字がつぶれて印刷が悪い上に、訳語は旧字旧仮名、ところどころ古い言い回しがある。しかし、たとえば”deliberate”の項など”Deliberate in counsel, prompt in action.”とあり、訳語が「始めは處女の如く終りは脫兎の如し」などとあって、なかなかおもしろい。
ふと”Greek“に目をやると「希臘人 希臘語」と訳語! 例文には”It is (all) Greek to me.”というのがあって「ちんぷんかんぷん、さっぱり譯がわからぬ、唐人の寝言」と訳があててある。なるほどうまいこと言うなあと、いたく感心した。ちょうど日本人にとって漢字文化のご本家の中国語が分からないように、イギリス人も欧米文化のルーツであるギリシア語が「ちんぷんかんぷん」なんだと……。しかしまあ、そんなことを喜んでいるぐらいだから私の受験勉強もおぼつかないものだったが、とにかく高校を卒業し、大学に入ることは入った。
その後、ふとしたことがきっかけで柳沼重剛氏の『語学者の散歩道』という本を読んでいると、なんと「’It‘s Greek to me’考」という一文にぶつかった。それによると、この句はシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』の中で、暗殺団の一人・キャスカが言った台詞。キケロの言ったことがチンプンカンプンだったというのと、それがギリシア語だった、というのをかけた洒落になっているという(当時のローマの上流階級はギリシア語を話すのが普通だった)。柳沼氏のすごいところは、この英語の言い回しはシェイクスピアの発明ではなく、実はそれ以前に5つの例があり、しかもイタリア伝来のものではないかというのだ。さらにフランス語でチンプンカンプンは、”C’est de l’hebreu pour moi.”といい、いずれも「わけのわからない言葉」の代表として引き合いに出されていることに着目している。つまりギリシア語もヘブライ語も、ヨーロッパで一般に使われている字(ローマ字)とちがう文字で書かれていて、そう簡単によめないこと、「近寄りがたくむずかしい」また「すぐれた、尊敬すべき」言葉だと思われていること、言いかえれば、人々が「敬して遠ざけている言葉」であるというのだ。
柳沼氏は話のついでに、ドイツ語では”chinesisch”(時にフランス語でも”chinois”=いずれも中国語)というと紹介しているが、西欧の人々にとって漢字がチンプンカンプンなのは当然として、私がふと思ったのは、西欧におけるギリシア語やヘブライ語の位置は、東アジアにおいては漢文に相当するのではないかということだ。
ちょうど聖書がギリシア語やヘブライ語で書かれたように、東アジアでは『論語』や『般若心経』などの経書(ケイショ)やお経(キョウ)は漢文で書かれた。漢文はまさに「そう簡単によめない」「近寄りがたくむずかしい」「すぐれた、尊敬すべき」、人々が「敬して遠ざけている言葉」と見なされてきた。
国語辞典を見ると「チンプンカン(プン)」は、「儒者の用いた難解な漢語に擬した造語とも(『大辞林』)」、「儒者の用いた漢語をひやかしていったところからとも(『大日本国語辞典』)」とあり、その語原が漢文の難解さにある可能性を指摘している。
齋藤秀三郎氏が『英和中辞典』において、”It is (all) Greek to me.”を「ちんぷんかんぷん、唐人の寝言」と訳したのは、まことに「言い得て妙」というほかはない。いまどき英和辞典の例文に「唐人の寝言」などという訳をつける人もなかろうが、それにしても荒削りのようでいて、まことに正鵠を射た訳であったわけだ。
ところで「唐人(トウジン)」とは誰のことだろうか? 普通には中国人、とくに江戸時代に長崎あたりにきていた中国人をイメージするが、外国からきた人一般をさす場合もあった。「唐」には「から」という訓があるが、古くは「韓(から)」、特に朝鮮半島南部の「加羅(伽羅)」をさし、転じて朝鮮半島、さらに中国をメインとする外国という意味になっていったようだ。「唐(トウ)」の字に「から」の訓が当てられるようになったのは、中国の王朝の「唐」が成立して以来のことではないだろうか。「漢」の字に「から」の訓が与えられているのも同様な事情によるものと思われる。
「唐」は、政治的に強大であっただけでなく、東西文化交流の中心として、日本など周辺の国家・民族に大きな影響を与えた王朝であり、自国の歴史や文化に強い自負をもっている中国人が、特に誇りとするところだ。
中国の大学で日本語を教えていた時、学生に自国の歴史のなかで一番好きだと思うのはいつの時代か、と聞くと、口をそろえて「唐朝」という。北京の街中を歩いていても、時々「大唐」「悠唐」など「唐」の字の名前をつけたビルや別荘にぶつかる。伝統的なもの、なにか由緒あるもの、さらには隆盛とか豪華などの気分を表すのによく使われる字だ。


(左)北京市内のショッピング・センター (右)北京郊外の別荘。「観」は高殿の意か。
さて、「唐」から絶大な影響をこうむった日本において、この字が中国を意味したとして何の不思議もないわけで、「唐船」「唐物」「唐辛子」、「唐紙」「唐草」「唐様」など、「トウ」であれ、「から」であれ、実際にそうかどうかは別として、「中国モノ」を意味する言葉は掃いて捨てるほどある。その中で注目すべきは、寝言であったにしても「唐人」がしゃべっていたはずの「唐音」「唐話」であろう。
普通「唐音」とは、ご存じのように呉音・漢音のあと平安中期から江戸末までの間に日本に入ってきた漢字音をいう。結構長期にわたっており、中国の時代でいえば宋・元・明・清、主として江南・浙江・南京・福州などの南方の地域の発音が日本化したもので、「行灯」「椅子」「石灰(シックイ)」「蒲団」などがよく知られている。が、それは呉音や漢音のようにまとまって、あるいは組織的に入ってきたのではなく、日本人が禅宗の僧や亡命してきた中国人などから学んだ中国語が単発的に日本化したもののようだ。
もともと日本人は早い時期から漢字とともに中国語を勉強し始め、遣隋・遣唐使、最澄・空海など役人・仏僧から、交易商人・船頭にいたるまで、中国語を話せる人がかなりいて、文章も中国音で頭から直接読んでいたはずだ。それが9世紀末に遣唐使が廃止となるや、中国と直接交渉する必要がなくなり(つまり中国語を話す必要がなくなり)、それとともに中国の文章や典籍は日本語の語順に置き換えて読むようになり、鎌倉時代には返り点・送り仮名をつかった「訓読」ができるようになる。中国からの情報は典籍や文書を読むことで十分えられるので、話し言葉としての中国語(「唐音」あるいは「唐話」)は、仏僧や貿易などほんの一部の人以外、必要なかった。こうして書面語としての「漢文」のみが重視される時代が続くようになる。
本家の中国はというと、歴史的にみて漢字が読めるのは社会の上層の人々だけである。特に儒教の経典が重視され、高級官僚になれるのはその儒教の経典を丸暗記して科挙に合格した者だけ、というような極端な文字社会であり、文語で書かれた経典や文書と、日常生活語としての口語は大きく乖離する傾向にあった。日本においては上層の教養人が訓読で漢詩・漢文を読むだけだったが、江戸時代に入って儒学が尊重されるや、儒学者が難しい中国の古典を訓読・解釈するのが流行し、寺子屋で『論語』の素読をやるところもあったらしい。しかしまあ、庶民のほうは「儒者の用いた漢語をひやかして」「チンプンカンプン」といったりする程度であっただろう。
ところが、このような江戸の風潮のなかで、真剣に唐話(中国語)を勉強した人たちがいる。その代表は荻生徂徠だ。徂徠は、中国の典籍を日本の訓読法で読むのはおかしい、古典といえども中国語なのだから、ひっくりかえらずに頭から唐音(中国語音)で直読して初めて正確な意味が理解できると主張した。そして、唐通詞(中国との交易にあたった通訳・事務官)を中心にした唐話学が盛んであった長崎から来た岡島冠山について、自ら唐音・唐話を習ったほか、江戸に来た禅僧など、あらゆる中国人をつかまえて勉強したという。徂徠は同じく唐話ができた柳沢吉保の儒官となり、中国好き・学問好きで知られた将軍・徳川吉宗の前で唐音・唐話で古典を講じたこともあったらしい。
そんなことを私が初めて知ったのは、友人から「おもしろい本があるぞ」といって送られてきた信州の篤学者・埋橋徳良氏の著『日中言語文化交流の先駆者 太宰春台・阪本天山・伊沢修二の華音研究』によってであった。埋橋氏は、信州出身の学者たちの中国語研究の業績を分かりやすく、また情熱をこめて書いている。
また江戸初期の日中関係や、吉宗の君臨した享保年間の文化状況については、博覧強記の歴史学者・大庭脩氏の『徳川吉宗と康煕帝―鎖国下での日中交流』に詳しく、いろいろと興味深い話を載せている。
ただ徂徠以下、春台・天山たちの主張はといえば、その後大きな学問的な流れになることなく明治を迎える。
明治になると、世はこぞって欧米の文化を吸収するのに夢中となる。漢文は国語の一部として学ばれはしたものの、現代語としての中国語は独仏英語のまえに影のうすいものとなっていく。その傾向は日清戦争において、かつての超大国・中国の実力のほどが露呈してからというもの、ますます強まっていった。
安藤彦太郎著『中国語と近代日本』によれば、戦前、旧制の高等学校・大学というエリート・コースで学ばれたのは英語・ドイツ語・フランス語で、中国語・ロシア語は第一はもちろん、第二外国語としても設置されたことがなく、中国語はもっぱら商業学校、外語学校などの専門学校にまかされていたという。古くは唐話、明治になり漢語、清語、清国語、そして支那語、華語、中国語(甚だしい場合は満州語、満語と誤称)と多様な名称があったようだが、まさに日本における中国語の位置を象徴するような話だ。近代日本が関わった4つの大きな戦争(日清、日露、第一、第二)のどれにも中国が大きく関係するなかで、中国語は商用と戦争のための道具といった見方が強くなっていく。
私が不思議に思うのは、中国語が軽視されるちょうどその明治・大正の時期に、『漢文大系(冨山房)』『正続国訳漢文大成」(国民文庫刊行会)』『漢籍国字解全書(早稲田大学出版部)』『有朋堂文庫漢文叢書』『校註漢文叢書(博文館)』など、目を奪われるほどの厖大な漢文の叢書が続々と発行されていることである。
中国の古典文化への崇敬の念と、現実の中国に対して繰り返し行われた侵略と蔑視、この矛盾をどう考えたらいいのか? それは過去の栄光と眼前の混迷という、当時の中国の姿そのものともいえるし、また日本人の相反する中国観の現れともいえるだろう。このような中国観は現代においても残っており、たとえば第6回「礼に始まり……」で紹介したが、「かの国にホント孔子が居たのかな」という川柳などに典型的に表れている。
中国語の地位は、中国が中華人民共和国となり、私が大学に入った1960年代になってもそれほど変わりなかった。時代は東西対立の真っ只中、英語(米語)の盛況はもちろんとして、ちょうど実存主義が花盛りでフランス語はモテモテ、医学・哲学のドイツ語もがんばっていた。ロシア語は共産圏の重要な言語であり、ちょうどソルジェニツィンがマスコミで話題になっていた。というわけで中国語を選択する学生はスペイン語より少なかった。
私が中国語を学んでいるというと、不思議そうな顔をされた。中にはなぜか、「あの~、ご実家はお寺さんですか?」などと聞く人までいた。唯一救われたのは英語の先生から言われた一言。「語学は大学で単位をとったぐらいでは役にたたない。本当にものにしようと思ったら、せっかく東京にいるんだから語学学校に行きなさい」。私は倉石中国語講習会に参加した。倉石とは中国語教育の先駆者ともいうべき倉石武四郎氏、講習会は今の日中学院の前身であるが、まわりにはイデオロギーに走る人が多く、アテネ・フランセや日仏学院、ゲーテ・インスティテュートなどにくらべると、かなりジミな存在だった。
その後中国は文化大革命をへて改革開放に向かい、GDPはついに日本を抜いて世界第2位になり、いまやアメリカを追い抜きそうな勢いである。日本における中国語学習者の数も増え、英語についで第2位だという。強い国の言葉が学ばれるのが世の常だ。
強い国の言葉といえば、昨年ギリシアを旅している時、みやげもの屋で懐かしい言葉に遭遇した。”It’s all Greek to me!”
かつてヨーロッパにおいて、「近寄りがたくむずかしい」「すぐれた、尊敬すべき」といわれた栄光のギリシア語が、なんとTシャツとなって売られていた。西欧の歴史に燦然と輝くギリシアは、いまやユーロ圏のお荷物とまで言われている。
さて、悠久の歴史を誇る東の大国・中国が経済のみでなく、文化においても「大唐」の栄光をとりもどす日は近いのだろうか?
(c)Morita Rokuro,2016